11/29 音符を覚えるには…
12/20 欲と意地
12/21 地域交流会
12/24 スケート
1/2 やられた〜!
1/4 スタートは…
1/4 相互リンク
1/5 元旦
1/23 逮捕
2/3 米寿
2/4 シニアのためのピアノ教育メソード
2/9 シニア歓迎ピアノ教室(^-^)/
2/16 先生の苦悩=踏みっぱなしペダル
2/20 謎の解明
2/26 シニアのペダル‐結論
![]()
| 2005年11月29日(火) 音符を覚えるには… |
見て見て!
83歳生徒Sさんが、ご自分で作ったものです。
「トシで、覚えが悪くなったので…」
と、こんな方法を考えていらっしゃいました。
見て見て!
そうしたら、77歳生徒Cちゃんが、
「私は、こんな風にして・・・」
と、手帳を開いて見せてくださいました。
これなら、病院の待ち時間でも見ていられます。
皆さん、色々な工夫をなさっているのですね。感激!
・・・ああ、子供では決してあり得ないこと。
こんな熱心さや前向きな姿勢を目の当たりにすると、
私も、少しでも良い指導法を工夫しなくっちゃ…!
という気持ちになってくるのでした。
(*もし、「自分はこんな方法で覚えています」というのがあったら、教えて下さいね。紹介します。)
| 2005年12月20日(火) 欲と意地 |
今日は「第19回−60歳からのホームコンサート」。
生徒達にとっても、良い刺激になるようですが、
私にとっても、いつも発見や驚きや収穫があります。
信じられないようなことが起こったり、
60歳以上の学習者の新たな特徴を発見して考えさせられたり、
子供ではあり得ないほのぼの発言に心が暖かくなったり、
皆さんのピアノへの想いや情熱を改めて知り、身の引き締まる思いがしたり、
60歳以上でピアノを習う素晴らしさを改めて感じたり・・・
こんな発言に爆笑。
Aさん:「人生の時間が少ないから、少しでも多くピアノを弾きたいという欲があって…。
私は、その『欲』でピアノを弾いているの。」
Bさん:「『欲』ですかぁ。僕は『意地』で弾いています。」
私は「向上心」と思っていましたが、実は「欲」や「意地」だった?(^◇^)
でも人間、そんな欲も意地も向上心も失い、努力しなくなったら、最後。
このような素敵な笑顔もキラキラした目の輝きも消えてしまうのかも知れません。
| 2005年12月21日(水) 地域の交流会 |
小学校児童館で、地域の世代間交流の会がありました。
60歳からのピアノの生徒達・OB・OGの皆さんが、2歳くらいの子達相手に本当によくやって下さいました。
折り紙を沢山折ってきて、子供達に紹介して下さったCちゃん、
暖かい司会で盛り上げて下さったMちゃん、
手話コーラスを全部覚えて皆に指導くださったNちゃん、
「きよしこの夜」を英語で独唱してくださったKちゃん、
パズルと手品を合わせた造語「パジナ」を考案して紹介してくださったSさん、
伴奏やアシスタントや何かと皆を支えて下さっていたKさん、
尺八演奏やマジックを披露して下さったHさんとお友達
・・・皆さん、本当にご苦労様でした。
今年は、昨年よりもっと小さいチビちゃんと触れ合え、また一味違った会となりました。
皆さんのおかげです。ありがとう!
| 2005年12月24日(土) スケート |
スピードスケートのようなタイムで決まる競技ならば、どちらが高順位か誰にでも解ります。
しかしフィギュアスケートのように、美しさで決まる競技は、素人と専門家と一致しないこともしばしば。
素人は「この選手の演技が、一番華やかで素敵で1位に違いない。」と思うのに、
専門家のジャッジによると、あまり点が出なくて下位ということもあります。
反対に、素人が「この選手の演技は、見ていてあまり面白くないし、点が低いだろう。」と思う演技が、
専門家のジャッジは、高得点ということもあります。
どちらかと言えば、ピアノはスピードスケートよりもフィギュアスケートに近く、素人と専門家との感じ方の差が大きいように思います。
| 2006年1月2日(月) やられた〜! |
12月30日・・・大掃除、年賀状書き、おせちの用意、新年を迎える準備・・・
さあ、頑張るぞ!(^-^)/
と思いきや・・・
やられた〜!!「お腹を壊す風邪」に。
気持ち悪い、吐きそう、ううっ、寒気、ぶるっ。
何も食べずイオン飲料だけで、ひたすら布団に包まって寝る。
やっとおかゆが食べられるようになった頃、気づくと世の中もう2006年。
何もせずに新年になってしまいました。最悪。
| 2006年1月4日(水) スタートは… |
風邪のため、まだ私は「2005年とのお別れ」も「2006年の開会式」もしていません。
ピアノを教えているシニア達から、こんなことを習いました。
「スタートが遅いということはない。」
そうです。いいことを思いつきました。
時計の針を少し戻してしまうことに致しましょう。
今日1/4を、12/31(大晦日)ということにするのです。
だから今日は、お掃除、買出し、年賀状書き、新年を迎える準備…。
明日1/5は、1/1(元旦)ということにします。
少し遅れたけれど、私の2006年は明日からスタートします。
「スタートに、遅すぎるなんていうことはな〜い!(^-^)/」
| 2006年1月4日(水) 相互リンク |
家の中の整理もですが、パソコンの中の整理も。
ゴミ箱を空にしたり、出しそこなっていた返事メールを出したり、一年分を整理。
ホームページのリンクの張りっこ(相互リンク)しているページをクリックしてみると、半分以上のサイトが無くなっていました。
残ったのはたった四分の一位。
更新が負担になって閉めたり、サーバーの期限が切れたり、色々な事情があるのでしょうか。
私のページもあまり頻繁に更新できないのですが、でも細く長く続けたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
| 2006年1月5日(木) 元旦 |
1/4が私の大晦日なので、今日1/5が私の元旦ということに…。では、
新年、おめでとうございます☆
本年も、60歳からのピアノのレッスンに、
指導法研究に、一生懸命がんばりますので・・・
どうぞよろしくお願い致します☆
| 2006年1月23日(月) 逮捕 |
ホリエモン(そんな悪人そうに見えないけど)の逮捕、
姉歯や小嶋(見るからに悪人そう)の偽装・・・様々なニュース。
2歳位のこと、一人で遊んでいて結構深い池に落ちた記憶がある。
「人間は酸素が必要」「水中では空気を吸えない」などという理屈は全く解らないのだが、体が苦しい。
池の上の方に行くと少し楽だけれど、底がヌルヌルしていて滑ってしまい立っていられない。
また底の排水溝あたりに行ってみるが、その辺は体が苦しい。
水中を上に向かう泡が綺麗だった。
顔が出るか出ないかの水面近くは少し楽。でもすぐに滑って転んでしまい、水中に。
・・・そんな繰り返し。
溺れ死なずに今も生きているということは、誰かに見つけられたのでしょう。
この世に生を受けた以上は、ささやかでもいいから良いことをしていたい。
「人のため」「お国のため」みたいな偽善っぽいのは嫌だけれど、
でも、少なくともラクして利益を得ようとするズルイ人、世の中の悪人にはなりたくないものです。
| 2006年2月3日(金) 米寿 |
私は、夫の母と同居しています。
今日は、義母のことをお話し致しましょう。
「ピアノを弾けない」どころか、リウマチのため指が動かずボタンをかけるのも大変。
その上、骨折で車椅子となり要介護3なのでヘルパーさんにもよく来てもらっています。
年齢が年齢なので排泄など失敗することもありますが、
卑屈になったりイジケたりせず「ごめんなさい」と素直に謝り、
助けてもらった人にいつも感謝の気持ちを忘れません。
老人の話題に多いとされる「人の悪口」「自分の自慢」などは一切しないし、
話していて楽しいので、親戚、お友達、色々な方が電話や訪問をしてくださいます。
今日は88歳、米寿のお祝い。
プレゼントは何がいいかしら?
調べたら、「米寿は金茶色のちゃんちゃんこ」
と書いてあったので、「こげ茶色のカーディガン」を買ってきました。
私自身が着るものは、貧乏学生だし安いものばかりですが、
義母には、軽くて暖かい高級カーディガンを奮発しました。
胸元のビーズ飾りがちょっとお洒落。(^-^)
ここまで来たら、90歳まで、いえ100歳まで長生きして欲しいものです。
がんばれー!(^-^)/
| 2006年2月4日(土)60歳以上のピアノ教育メソード |
修士論文「60歳以上初心者のためのピアノ教育メソード −理論と実践からの構想−」
というようなものを提出してあります。
第1章に、60歳以上のピアノ教育に関する指導書もメソードも無く、研究が遅れている現状を書きました。
第2章では、ピアノ指導法を考えるのに、その年齢の学習者の「特徴」を明らかにすることが重要と考え、
「60歳以上の学習者の特徴」について考察しました。
まず自分の5年間の実践から「13の特徴」を仮説としてあげ、
文献と実験から、その仮説の検証を行い実証。
第3章では、その特徴から、60歳以上を対象としたピアノ教育の「理念と方法」を導きました。
第4章で、前章の理念と方法に則った「ピアノ教育メソード」を構想しました。
そしてナント、ふ・ふ・「ふ・ろ・く」まで付いているのです。(^◇^)
教則本を作って付録にしたのです。
130ページの本体と60ページの付録を前に、なんとも言えない気分。
22日に口述試験、27日に発表があります。どうか通りますように。(^人^)
| 2006年2月9日(木)\(^-^) シニア大歓迎ピアノ教室(^-^)/ |
「習いたいのですが、60歳以上にも喜んで教えてくれる先生を、私の近所で知りませんか?」
というメールをよく頂きます。
確かに「幼児に教えるのが大好き!」「受験生を音大に入れるのが得意」・・・
ひとくちに「ピアノの先生」と言っても、得意不得意があるのは当然。
「才能ある子をコンクール入賞させるのが好き」な先生に70代初心者の生徒が入ってきても、
一体どう教えたらよいのか見当もつかず、内心、「困ったわ。」と思われるのも当然です。
しかし一方では生涯学習指導などの勉強もして「60歳以上の生徒に教えてみたい」と思い、
待っている先生もいらっしゃいます。
そこで、全国の「シニア歓迎ピアノ教室」のリストを作ることにしました。
| 2006年2月16日(木)先生の苦悩=踏みっぱなしペダル |
ペダルというのは、踏み替えるべきところで踏み替えないと、汚い不協和音が響きます。
耳障りな雑音のため、「やめて〜!」と感じます。
しかし、耳障りで汚いと感じない、いえむしろその方が「素敵」と感じる人もいます。
私も小さい頃、ペダルを踏むと「お風呂場で歌った歌」「エコーをかけたカラオケ」のように、なんだか上手になった気がしたものです。
「ちゃんと習うまで使っちゃダメ!インチキペダルを踏んでいると、下手になっちゃうのよ。」
と、注意されたものです。
先日、72歳の女性がこう言いました。
「ペダルを正しく踏み替えられていないのは解っているのですが、
でも踏んでいた方が、ピアノの素敵な雰囲気に浸って、自分がとっても幸せな気分になってくるんです。」
人生の残り時間が少ない人の場合は、
「ペダリングが正しいかどうか」よりも「自分が幸せかどうか」の方が優先する気がしてきた。
そして自分の中で、二人の私(真面目ひろみ&柔軟ひろみ)がこんな葛藤を始めたのです。
柔軟ひろみ: 専門家になろうというのではないのだから、
目を瞑った方がいいのでは・・・?
真面目ひろみ:でも、「踏みっぱなしペダル」が癖になると、
どんどん直すのは困難になる。
そして麻薬のように、今度はそれが無いと「物足りない」
と感じるようになるもの。
初期のうちに、キッパリとやめさせた方が親切では・・・?
柔軟ひろみ:本人が満足で、幸せと感じるのならば構わないのでは・・・?
真面目ひろみ:独学ならともかく、お金払って習っている人とは思えない。
本人が「楽しい演奏」と、本人さえ満足なら「どうでもいい演奏」
とは、ぜったい違うと思う。
柔軟ひろみ:踏み替えたペダルが理想だけれど、
右手と左手と足と3つ同時になんて考えられないから、
仕方なく踏みっぱなしにしているのよ。
加齢のために難しいけれど、でも素敵な気分に浸りたいから、
インチキは百も承知でやっているのよ。
もっと柔軟に考えてあげたら?
真面目ひろみ:うーん・・・(苦悩)
・・・この年齢層の場合は、どうするのがベストなのか?
と一生懸命に考えて、悩み、試行錯誤し、
少しでも「その人にとっての良い指導」が出来るように・・・。
頑張ろうっと!
| 2006年2月20日(月) 謎の解明 |
ヤフーで「ピアノ」「ペダル」「踏みっぱなし」というキーワードを入れて検索してみたところ、 やっと謎が解けました!見つけた文章を引用します。
・・・ 「独学の人」や「先生について日の浅い人」には、結構いるのですね。
- 「独学でピアノをや ってきた人の中には、何でもどこでもペダルを踏みっぱなしの人もいる」
- 「ちゃんとレッスン受けるまで、家の電子ピアノで適当に踏みっぱなしで 「ふふーん」とかやっていたんだけれど、「そんじゃ駄目」という先生の指導により踏み変えという技術を習いました。」
- 「あとはペダルの修正。油断すると、すぐ踏みっぱなしになります(^_^;」
・・・なあるほど。電子ピアノで練習している人の場合、ペダルを踏みっぱなしでも、響く効果が半分位のため、それ程濁って汚く聞こえない。
- 「電子ピアノは濁らないんだが、アップライトではかなり濁って聞こえる。」
- 「先生の所ではグランドピアノを弾くのですが、ペダルを踏みっぱなしだと音が混じりすぎて しまって綺麗じゃなくなるんですね。」
- 「電子ピアノは、10年くらい前のものですが、それでも、 さすがに電子ピアノだと『ダンパーペダル』と『ソフトペダル』については『ハーフペダル 』に対応しています。」
(ハーフペダルとは、わざとペダルを半分位しか踏まず、 響く効果を少なくするテクニック)
- 「1800年代前半のピアノは、現代ピアノほど音が伸びず、響きも豊かではなかったために、ペダルを踏みっぱなしでもあまり問題なかったようです。」
1800年代のピアノのように、あまり問題はない。
でも、それと同じ事を教室のグランドピアノでやると大変なことになる。
そういうことだったのですね。そうかぁ。。。謎が解けました!!
| 2006年2月26日(日) シニアのペダル―結論 |
ペダルを踏んだままの原因は、右手・左手・足と「複数のことを同時に行う難しさ」と思われます。
昨年の実験によると、左右の手が異なるリズムや異なる強さをつけるのは、年齢とともに難しい結果となりました。
手と足の巧緻性も同様で、ペダル操作は若い人より難しいようです。
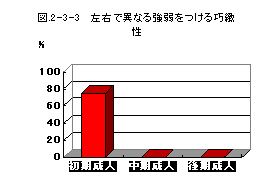
また、左右で異なる指を折るのに時間がかかってしまい、両手で弾けるようになるまでに多くの時間が必要です。
やはり「二つ以上のことを同時にする」のは、年齢が上がるほど難しいようです。
あまり負担が大きすぎては学習が楽しくありません。
そこで、次のような結論を出しました。
60代………踏み替えペダルを目指す。
へんな癖がつくといけないので「踏みっぱなし」はナシ。
70歳以上…踏み替えが出来ればもちろん良いけれど、
うまく行かない場合は「踏みっぱなし」もアリ。
発達段階の特徴に配慮した指導、エイジングに適合した指導法が、
その人にとって最も楽しくピアノを学べるのではないかと思うからです。
以前、70代の方が、ペダルなど使わずに「早春賦」を
実に心のこもった「味のある演奏」をして下さったことがあります。
そんな演奏こそ、子供には出来ない演奏、長く生きてきた人にしか出来ない演奏であり、私は聴いているのが好きです。